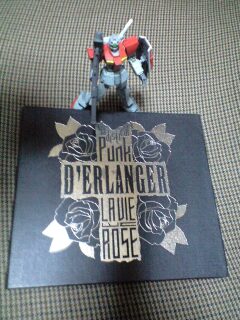前回は、DIZZY脱退から『LA VIE EN ROSE』前夜までを書いたのじゃった・・・
ふう・・・
デランジェ / ラ・ヴィ・アン・ローズ (1989)
D’ERLANGER / LA VIE EN ROSE
Kyo加入後、イヴェントなどで試行錯誤感が見てとれるライヴを何度か目撃してきた。
脱メタル、ビート・ロックへの接近とゆう流れで、新しい音楽性はまだ確立しているようには思えず、危うい感じのライヴを観るにつけ、バンドが後退しているようにも思えた。
しかしバンドは着々と次の一手を準備していたようだ。
そして、リリースされた1stアルバム『LA VIE EN ROSE』。
当時はアナログからCDへの転換期で、このアルバムはCDフォーマットのみでの発売となった。
収録曲中3曲はDIZZY在籍の後期に、既にライヴで披露されている。
そしてもう1曲『Sadistic Emotion』はさらに遡り、彼らがまだ完全にメタル・バンドだった時代からの曲で、スピード・ナンバーのEP『GIRL』の頃、既にこういったタイプの曲も作れたセンスは特筆すべきことだろう。アルバムに収録されるにあたって、ギター・ソロの前にあったバラード・パートがオミットされている。
CIPHEギターは『GIRL』の頃とは打って変わり、歪みを押さえて、曲ごとにハーモナイザーやコーラス等のエフェクター、クリーン・トーンを使い分けている。
SEELAベースは複雑に動き、ルートを刻むスタイルのビート系バンドとは一線を画している。
TETSUは、高速で細かいハイ・ハット捌きを多用するスタイルで、“日本のアクセプト”と称されたパワー・メタル・バンド、メフィストフィレスで叩いていた頃からすると、かなりの変化だ。速いのはツーバスを踏むスピードではなく、ハットの刻み方になった。
Kyoのヴォーカルは相変わらず線が細いが、バンドの方向性が絞れてきているので曲にマッチするようになってきている。そしてこの、ヴォーカル・スタイルは、‘90年代に大量発生するヴィジュアル系バンドの雛形になっていった。
後のシーンで、Aメロ部分でテンションを殺して歌ったり、鼻から抜け、しゃくり上げるような歌い方のシンガーが多かったのは、Kyoがデランジェに持ち込んだ歌い方が後発バンドからバンドへと伝言ゲームのように引き継がれていくうちに、特徴の分かりやすい部分が純粋培養、デフォルメされていったからではないだろうか。(同じ時期にZi:KILLのTUSKもいたが話が長くなるのでここでは触れない)
アルバム中でもっともデカダンな香りを放つ『An Aphrodisiac』。所謂ロック・コンサートのノリにおいてはセット・リストのハイライトとなる場面ではリフレインを伸ばして客席と一緒に歌ったり、「Hey!」や「Oi!」などのフレーズを連呼させて盛り上がりを演出するが、Kyoはライヴ中この曲で、言葉にならない絶叫を繰り出したり、取り憑かれたように「ラララ♪」を繰り返すなど、それまでのロックにあったマッチョなコミュニケーションとは逆の、狂気を体現すようなパフォーマンスを生み出した。
メジャー・キーのポップ・ソング、『Lullaby』は、バンドの方向性の変化とゆう視点では、アルバム中もっとも突き抜けた存在だろう。『GIRL』の頃からは想像もつかない爽やかな曲調だ。
アルバム全体として、出来たばかりのコンクリート打ちっ放しで作られた部屋に入ったような、ガランとしたサウンド・プロダクションで、'90年代以降の目線で見るとまだその筋のバンドのプロト・タイプといった感もあるが、この作品に影響されたバンドやさらにその子孫達が、後のシーンを形成していった。
個人的にはDIZZY在籍時、'87年後半~'88年初頭辺りの音楽性でアルバムが製作されたら、どんなぶっ壊れたグラム・メタル・ロックンロールアルバムが生まれただろうと想ってしまうが、そうするとその後に発生するシーンの歴史自体が大きく変わってしまっただろう。
『LA VIE EN ROSE』は、そんな時代の分岐点として産み落とされたアルバムではなかろうか。
「ではなかろうか」・・・つうか長いよ!
あ~ちかれた。
ぱかやろ~。(杉兵助)
 | LA VIE EN ROSE
(1995/04/21) |